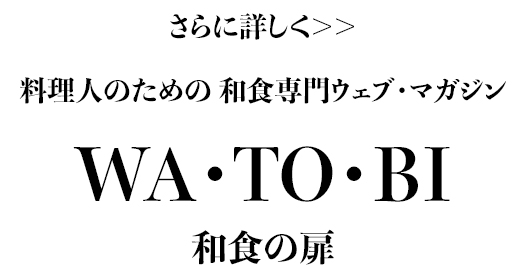新谷 亮人
上方中華 新瓊
大阪で中国料理店を営む家に生まれ、幼少期より中国料理人を志す。神戸、京都「青冥」、千葉「知味斎」で湖南・四川料理を学び、2006年に大阪にて「中国采 老饕」を開業。15年間、同店にて王道の中国料理を中心に提供し続けた後、2022年に「上方中華 新瓊」をオープン。関西ならではの、大阪だからこそ出来る中国料理を身上とし“上方中華”と提唱する。
日本の食の発展に大きく貢献してきた‘大阪の食’に魅力を持つようになりました。
歴史ある食文化を学び、培ってきた調理技術と掛け合わせ中国料理として発信出来ればとの思いで取り組んでいます。
調味料ではなく食材から出汁の深みや旨味を引き出す
明治に入って大阪は海の玄関口として府庁を大阪湾にほど近い江之子島に置いた(現在の西区の阿波座から九条辺りの場所)。そして海外の料理店として府庁周辺に多くできたのが中華料理店であり、今もその名残りか世代を継いだ中華店が最も多いエリアとされているようだ。いわば大阪料理は中華料理を巧みに取り込みながら培われてきたともいえよう。また反対に大阪における中華は、その国内での在り方を大阪料理から学んでもきたのであろう。
さて、今回の試作はそのような中華的な視点から上方料理を考えたものと捉えてよいだろう。食材は大阪の季を見据えて櫻鯛。これを中華仕立の出汁で食する趣向。料理名の爽煮はいわゆる湯木貞一好みの沢煮ではなく上野修三好みの爽やか煮から着想を得たものと聞いた。スープ(出汁)にコストと時間をかける中華料理らしさがこうしたところにも覗える。櫻魚の粗等に昆布出汁に老塩水を合わせたものをベースとし、深みのある爽やかな酢味を持った酢辣湯(サンラータン)スープを作り、焼霜しそぎ造りした櫻鯛と共に鯛白子豆腐に旬の筍を味わうというもの。酸味は発酵食材などから、塩味は梅干等から抽出させることで可能な限りいわゆる調味料というものを使用しないというスタンスは、現代の和食料理人が忘れかけていた和魂漢才の心でもあるといえよう。
総評
「櫻鯛のスープが非常に澄んでいるのに驚いた」「和食といえば昆布に鰹節の出汁だが、この出汁はまさにそれに匹敵するだけの旨さが感じられた」など多くの賛辞が寄せられていた。質疑応答では老塩水の作り方についての答弁が続いた。
運営委員からは「出汁につぎ込まれた深味や雑味といったものが旨味に昇華されている。またそれだけでなく仕上げに用いられている香味油やムージャン油(木姜油)がとても良い仕事をしている。和食へのヒントとすべき点が多く感じられた」とのコメントがなされていた。