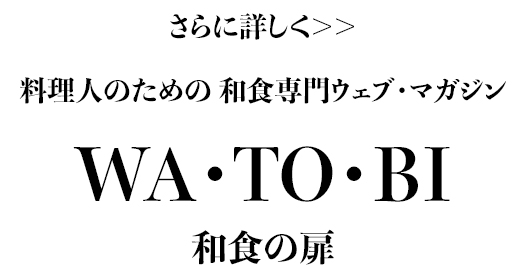岡本 正樹
天の川 なかなか
季節の御飯を客個々の竈で味わってもらう
竈(かまど)は、関東ではヘッツイ、関西ではクドとも呼ばれている。かまどの義は「釜処」で、食事を整え煮炊きをする場所をも意味した。形としては土、石などで築き、鉄釜をかけ燃料を差し入れ自然火で焚く。近世ではこれらを小型化したものを竈とも呼んでいる。電気やガスが主となっている現代では味わえないもののひとつともなっている。
今回の発表では、移動式の竈を自作したもので碓井豌豆の豆御飯を炊きその場で炊きたてを試食してもらうというもの。ここでの豆御飯は、生酒に干し椎茸や昆布を加えて冷蔵庫で寝かした出汁酒を炊飯水と合わせて用いている。
豆御飯の付け合わせには、乾燥させた蛍烏賊に味噌だまりを塗った「干し蛍烏賊炙り」。グレープシードオイルで炒めた「独活金平」。青パパイヤなどの根菜酢漬けなどが、五味五色を演出させる趣向として供された。最近、美味い米への関心の高まりから、日本料理店の中にも店内に大きな竈を据え、炊きたてを味わってもらうという店が散見されるようになった。しかし竈が本来は個々のものであったことを考えると、客ごとに移動式の竈という発想も面白いといえよう。
総評
「竈を自作しようという発案とその行動力に驚いた」「想像以上に早く美味く炊けることに感心させられた」などの評が聞かれた。
運営委員からは「竈はとても興味深いと思う。ただ豌豆御飯の炊き方にも、もう少し工夫があればさらに良かったのではないか。例えば米を炊く水に、豌豆の莢を湯がいた水を使用すると、さらに豆の香りが高くなるなど、豆御飯の工程そのものへのこだわりを期待したい」といったアドバイスがなされていた。