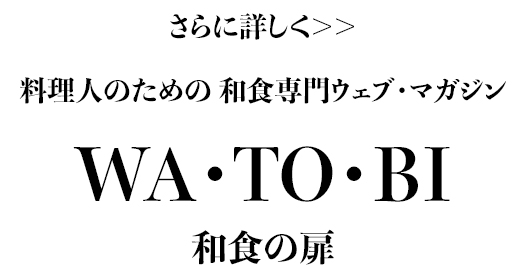城崎 栄一
旬屋 じょう崎
福岡県出身。神戸、奈良で修業後平成7年4月に吹田駅近くにお店を開業。魚菜の会で大阪産の食材を知り地元の吹田くわいなど伝統野菜、淀川天然うなぎ、能勢牛などを積極的に取り入れ会席と一品料理の両方を供する。スチームコンベクションを駆使して食材の最適な温度帯を探り現代的な日本料理と昔ながらの古典的料理を追求している。
始末の心で皮を活かし大阪野菜の魅力を再発見する
野菜好きに云わせると、野菜はじつは皮が美味いそうである。にもかかわらず野菜の皮は野菜屑として大半が廃棄されている。ここではそうした野菜ごとの皮を始末の心で活かすことから発案された大阪料理が披露された。
先ずは、勝間南京。南瓜の皮を剝き一口大に切り、揚げる。蒸し函に実と皮をならべ塩水をかけ蒸し焼きとしている。さらに蒸した皮を再度乾燥させこれをミキサーで香煎にし振りかけている。
次は玉造黒門白瓜。瓜の皮を剝き、実は塩梅した出汁で炊き上げる。皮は刻んで揚げた後に焚いた出汁に浸け込む。
三つ目は胡瓜。ここでは大阪の毛馬胡瓜のヒネを使っている。桂剝きにした胡瓜で、白焼きにし短冊にした淀川の天然鰻を巻き、これを八方出汁で炊くと共に炊いた皮をタレ焼きにして刻んでいる。
最後に泉州水茄子。同じく皮を剝いた水茄子の実と皮を揚げ、実は旨出汁で炊き、皮は実を焚いた出汁と共にミキサーにかけ葛引きし掛けている。
これらの野菜料理に使用した真昆布は出汁引きした後、水に浸けておく。これを同幅に幾重にも天上のごとく重ね時間をかけて佃煮としている。天上昆布とは大阪の真昆布で作ってこそ、そう呼ばれてきたのである。
総評
「まさに大阪料理会らしい料理で感心させられた」「何よりすごいのは、各々の野菜の特徴がシンプルな料理の中に最大限に発揮されていること」このような多くの賛辞が寄せられていた。また畑会長からは「いずれも見事としかいいようがない出来映えだが、中でも勝間南京が塩味だけでこれほどの濃厚な味わいを出せるものであることを再認識させられた」とのコメントの後に、「真昆布を再利用した天上昆布。今ではこうした仕事をする料理人はほとんどいない。次代へ継承する意味からも大切にしなければならないと考えさせられた」との感想が付加されていた。