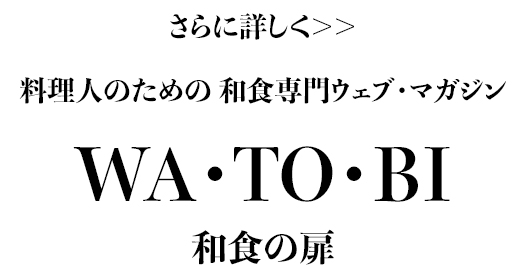長内 敬之
旬鮮和楽 「さな井」
大阪らしい工夫で水蛸を四季の料理に活かす
大阪の蛸といえば真蛸だが、最近では漁獲量が激減の一途であることから高級魚に比肩するまでになっている。さらにいえばいわゆる大蛸とされるものがほとんど市場に出ることがないので、今では水蛸を関西でどう活かすかが料理店の課題ともなっている。
今回の試作は、まさにそうした視点からの発表といえよう。ここで使用しているのが水蛸の足(2本800㌘)。この水蛸の足を塩ではなく、プーアル茶で揉み込み、真空パックに入れ山椒オイルを加え58℃で約25分間スチコンでスチームしている。仕上がった足を大細などに分けフードプロセッサで豆腐や片栗粉等と共に細かくした後に、さらに擂り鉢であたる。流し函にこれを流し入れ蛸の吸盤を埋め込む。これを蒸し器にかけたものを、水無月に切る。別途、新生姜の葛豆腐を作り、これを共に椀に盛り込み、沢煮らしく、干し筍に人参や絹莢、新牛蒡などを千切りにし、最後に一番出汁に玉子で吉野仕立てとしている。沢煮は、湯木貞一氏が夏場に川遊びし、清涼な沢の水際に寄せられた草木々を椀に見立てたものとされている。そんな沢煮に蛸水無月とは、いかにも大阪料理らしい粋(すい)が感じられる椀といえよう。
総評
「水蛸に新生姜の取り合わせは見事」「蛸の処理が非常に面白く参考になった」とする声が聞かれた。また参加会員の中からプーアル茶を使う理由についての質疑応答が多くあった。「ヌメリを除く効果に加え、タコ独特な臭みを除いてくれる」その効能について長内氏から説明がなされた。畑会長からは「タコの水無月も見事だが、野菜出汁を使った新生姜豆腐が素晴らしい」との賛辞が寄せられていた。