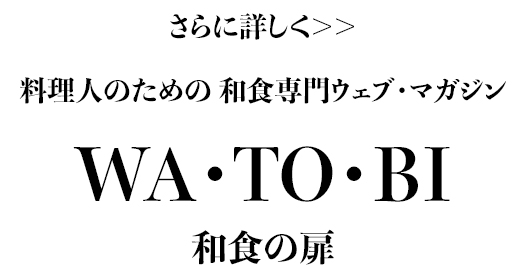山本 英
はしま
関西発祥の儀礼食を現代の大阪料理に活かす
関西では飛鳥時代に天武天皇が旧暦九月九日の重陽に菊花の宴を催した記録が残されている。以後、平安時代から我が国の例年の儀式となっている。こうした儀式食を大阪料理として取り入れることは意義深いことといえよう。
今回、菊花に合わせるのが帆立に干し椎茸そして秋茄子。塩をした帆立には焼き目を入れ、これをほぐし身にする。干し椎茸は常のごとく戻し調味した地で焚いておく。秋茄子は翡翠茄子とする。ここでは揚げるのではなく、茄子の皮を除いたものに穴を開け、塩水にて塩もみしたものを漬けることでアク抜きし翡翠色に仕上げている。
吸地には真昆布とシビ節で引いた出汁に淡口にて調味。固めものの椀種には豆乳を使った葛豆腐。下茹された菊菜ならではの味わいと平茸の柔らかな食感。これらが天に添えられた菊花と椀中で相まって、なんとも重陽の宴に相応しく面白い。ちなみに菊菜は、関東では春菊と呼ばれるが、日本へは戦国時代に入ってきたようで関西好みの菜物として現代も大阪府ではその生産量で上位占めている。
総評
「菊花の香りが何とも心地よい」「椀種はいずれもよかったが中でも椎茸の食感が素晴らしかった」「何より彩りが美しく感じられた」などの賛辞が寄せられていた。
畑会長からは「取り合わせの妙が見事であった。また椎茸は生では得られない干し椎茸の良さがよく出ていた。あえて云えば、ここまで味わいや彩りが揃ったものなら吸地は真昆布だけでよかったのではないか」とのアドバイスがなされていた。